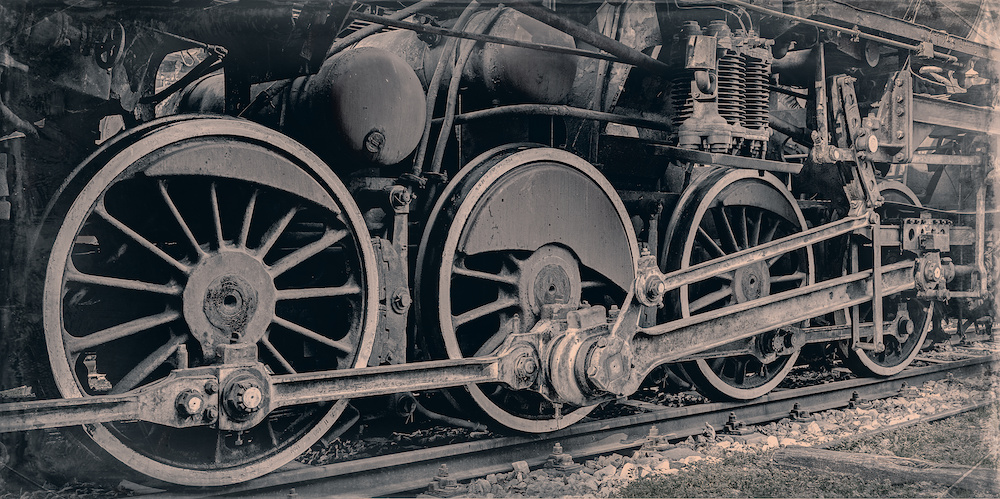世界は広大であり、異文化に満ち溢れており、さらに言えば豊かだ。すでに、地球は無限であるという20世紀的な考え方は成立しない21世紀になり四半世紀が終わろうとしている。世界に張り巡らされたネットの網目の上には、無数のコミュニケーションが乱舞している。そうした日々が繰り返され続ける現代において、世界を縦横無尽に駆け巡り、あらゆる出会いを蓄積しビジネスにしたら、これほど熱量の高いことはない。ヤマダイ食品グループにも、この時代の波に乗りながら、自由で制約のない法人格があったらどうか。その立ち振る舞いは、グループに対して、社会に対して、そして時代に対してどのように映るのか。どのような可能性を持ち、同時に、フィードバックしてくるのか。そうした挑戦と実験を実践していくために生まれたのがモカ・フード・ジャパンである。
実験場として。
「モカ」という名前ですぐに思いつくのはコーヒーだろうか。余談だが、モカコーヒーの由来はアラビア半島イエメンにある港の名前である。ここから出荷されたイエメン産やエチオピア産のコーヒーを総称してモカと呼んだのが始まりだ。日本だと、伊万里焼と同じストーリー。こちらは、もともと佐賀県にあった伊万里港(現在の伊万里市だが港はない)から出荷された焼き物を総称したのが由来である。細かく言えば、鍋島焼、吉田焼、有田焼などの磁器産地の総称として用いられることがある。
実のところ、モカ・フード・ジャパンの名称はこれらのどれとも異なる誕生秘話である。拍子抜けするかもしれないが、シンプルに創業者である樋口智一の名前の一部をとったものだ。TO“MOKA”ZU、でMOKA。海外放浪のようなことをした経験のある樋口は、常々あらゆる文化にまたがるようなビジネスを手掛けたいという野望を持っていた。世界を知れば知るほど見えてくる可能性と厳しさ、同時に無限のように多様な文化の価値に、強烈な魅力を感じていた自分と法人の未来の姿を重ね合わせ名前をつけた。最初に目をつけたのは“水を売るビジネス”である。水は人類にとって必要不可欠なものであり、万国共通のものでもある。

しかし、水ビジネスは大失敗する。最初は、名古屋に店舗を構えて水を売った。当時のことを、モカ・フード・ジャパン創設当時からのメンバーである高橋はこう語る「とにかく、必死で水を売りました。基本的に自分は店舗にいたのですが、お客様が全然こない。それならばと営業に行く。それでも売れない。まだ、日本で“ミネラルウォーターを買う”という文化が定着していないころだったのもありますが、それ以上にブランドとしての知名度のなさが大きな原因でしたね」。すぐにモカ・フード・ジャパンは、水ビジネスに対し早々に見切りをつける。店舗を閉め、販売もやめた。一方で、水の仕入れから始まったネットワークには大きなバリューがあった。そこで、商社機能にシフトしていくこととなり、現在の足がかりとなる。
文化を横断する。
モカ・フード・ジャパンはまだ始まっていない。たしかに法人としてはすでに存在しており、社歴も10年以上ある。海外から素材の仕入れも行い、国内に供給してきた。しかし、文化を横断し、ユニークな存在になっていくという物語はこれからだ。そうした中で、樋口が重要視しているのがタイに構えているモカ・フード・ジャパン子会社の存在である。現地の感覚は、すでに日本では手に入らないものばかりである。成長するマーケット、変動する経済、国家、政治、そして、どんどん切り開かれる新しい食文化。日本もかつてそうであったように、アジアは自国の食文化を革新させながら、さらに多様な食文化がどんどん花開いていくだろう。そうした高揚感があるし、スタッフもまた流動的な発想と、シビアな成長マインドを有している。
そもそも、世界経済における日本のプレゼンスはどんどん縮んでいる。GDP換算でいけば、1995年には世界において17.6%あったものが2010年には8.5%になった(内閣府のWebより抜粋)。2020年の実数はあきらかになっていないものの約5%と想定され、今後さらに落ちていく。というのも、日本の成長率は1%前後でしかないからだ。逆に世界の国々のダイナミズムは大きく、特に東南アジアの成長はめまぐるしい。タイというのは、その真っ只中にいる国のひとつであり、だからこそ子会社とは言え、タイの中で日々磨かれる意識も意欲も日本とは比べ物にならないほど高い。モカ・フード・ジャパンのバリューは、こうしたところから再び新たな芽吹きとなるに違いない。